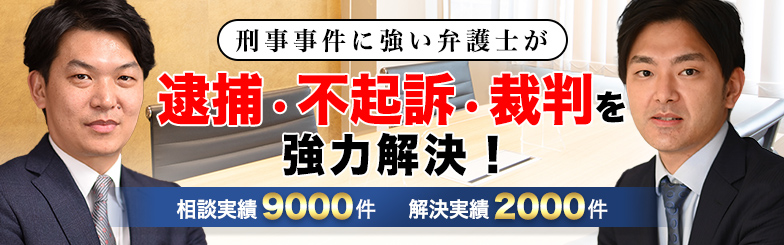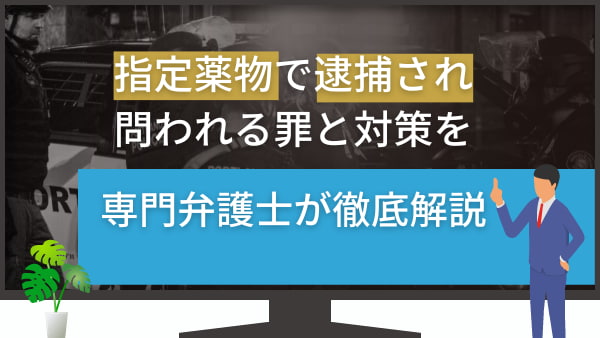
- 指定薬物で問われる罪とは何か
- 刑が下されるまでの流れを知りたい
- 弁護士はどんな活動をしてくれるのだろう
指定薬物で逮捕された場合は、早めに専門弁護士に依頼することが大切です。弁護活動によっては、本人の身柄拘束期間や量刑が変わる可能性があります。また、被疑者の再犯防止策も親身になって考えてくれます。
今回は薬物に強い専門弁護士が、指定薬物で逮捕された場合に問われる罪や弁護活動について詳しく解説します。
この記事を監修したのは

- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
宅地建物取引士
指定薬物で逮捕されるのか
指定薬物で逮捕されるのかについて、以下2点を説明します。
- 指定薬物とは
- 問われる罪
それぞれ、解説していきます。
指定薬物とは
指定薬物とは「中枢神経系の興奮もしくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」と、医薬品医療機器等法で定義されています。
たとえば亜硝酸イソブチル、亜硝酸ブチルなどがあり、現時点で指定薬物に指定されている物質の総数は2,000を超えています。
薬物として有名な覚醒剤、大麻、麻薬は指定薬物ではありません。指定薬物の他に、「規制薬物」「危険ドラッグ」と呼ばれる薬物もあります。規制薬物には覚醒剤・大麻・麻薬・向精神薬・あへんなどが含まれます。また危険ドラッグとは、規制薬物や指定薬物を含有する製品のことです。
「合法ドラッグ」「脱法ドラッグ」と呼ばれる薬物に関しては多くの場合、指定薬物が含まれていると言えます。
問われる罪
指定薬物で問われる罪について説明します。指定薬物の所持、使用などの行為は違法であり、罰則の対象です。
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で定められているとおり、所持・使用・譲り受け・製造などの罪に問われた場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
営利目的の場合は、さらに罪が重い傾向にあり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられます。
関税法でも定められており、指定薬物を輸入した場合は、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金(またはこれを併科)となります。
指定薬物の輸入で適応される法律は、かつては薬機法のみでしたが、薬物乱用者の増加が深刻化したことから、平成27年4月1日より関税法でも規定が加わりました。そのため、指定薬物を輸入した場合の罰則は、以前よりも重いです。
指定薬物で逮捕された場合、大半は起訴され有罪となり、厳しい罰則を受けることになります。
指定薬物で逮捕された後の流れ
指定薬物の所持や使用などで逮捕された後の流れについて説明します。
- 身柄拘束
- 起訴・不起訴
- 刑事裁判
それぞれ、解説していきます。
身柄拘束
指定薬物で逮捕されたら、まず最大72時間身柄が拘束されます。逮捕後の流れを以下表に記載します。
| 逮捕後、通算72時間以内 | 逮捕後、48時間以内
↓ |
警察による取調べ→検察官に送致 |
| 送致後、24時間以内
↓ |
検察官が裁判官に勾留請求
〈被疑者が罪を犯したと考えられるか、住所不定かどうか、罪証隠滅・逃亡のおそれがあるかなどが考慮される〉 (勾留請求されない場合)在宅事件 在宅事件の場合は身柄が拘束されず、日常生活を送りながら捜査や裁判を受けます。 |
|
| 勾留請求後、10日間 (やむを得ない事由があるときは最大20日間) |
勾留 〈警察官・検察官による取調べが行われる〉 |
|
指定薬物で逮捕されると、最大で72時間と20日間、警察署の留置場で身柄拘束を受けることになります。
起訴・不起訴
身柄拘束期間の捜査を経て、検察官は被疑者を起訴・不起訴(刑事裁判にかけるかどうか)を判断します。
検察官が起訴と判断した場合は、「被疑者」は「被告人」と名称が変わり、留置場から拘置所へと移送されます。一般的に裁判中も拘束が続くため、被告人の疲労は測り知れません。
起訴後は弁護活動によって保釈請求し、保釈金を支払えば身柄を一時的に解放してもらうこともできます。
検察官が不起訴と判断した場合は、被疑者の身柄は解放されます。その理由は「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」などがあり、不起訴処分になれば裁判が行われず、前科もつきません。
刑事裁判
起訴されると、刑事裁判が行われます。通常、第1回公判は起訴から1~2か月の間に行われます。被告人が起訴事実を認めている場合は、結審までの公判は1~2回程度、結審後2週間~1か月後に判決が言い渡されることが一般的です。
裁判の間保釈がなければ、原則として判決に至るまで身柄拘束が継続され、被告人は拘置所で過ごすことになります。
裁判で犯罪行為が軽微で争いがなく執行猶予が見込まれると判断された場合は、起訴から2週間以内に第1回公判が行われ、その日に判決まで言い渡される「即決裁判」になる場合もあります。
指定薬物犯罪の量刑は、犯行の規模・計画性、薬物の使用量・使用歴などによって判断され、多くの場合懲役刑を受けることになります。執行猶予が付くかどうかの判断は、本人の反省態度や再犯の可能性・周囲のサポート体制など、多方面の事由が考慮されます。
不起訴や執行猶予を目指す場合は、早急に弁護士に相談すべきです。各々の状況に合わせて対策を準備し、検察官や裁判所を説得することができます。
関連記事:指定薬物の執行猶予制度とは?専門弁護士が概要や条件・弁護活動について解説
指定薬物で逮捕された後の弁護活動
ここまで、指定薬物で問われる罪、逮捕後の流れについて説明しました。それでは指定薬物で逮捕された場合、弁護士に依頼するとどんな弁護活動をしてくれるのでしょうか。ここでは以下3つについて解説します。
- 保釈請求
- 治療や再犯防止のアドバイス
- 否認事件の場合
それぞれ、解説していきます。
保釈請求
指定薬物で起訴された後、弁護士は被告人の保釈請求を行います。薬物事件では、起訴前の釈放は大変厳しいのが現状です。理由には、被告人に薬物自体の証拠隠滅の可能性が疑われることや関係者のネットワークが多いことが挙げられます。
そのため、起訴後から刑事裁判までの間に一時的に身柄が解放されるように保釈請求をすることになります。
保釈請求の手続きは被告人本人でも可能ですが、勾留中の被告人には身柄の自由がないため、大変厳しいとされています。もし本人の保釈請求が認められても、保釈金を納めなければ身柄は解放されません。保釈金の金額は、100万円単位で設定されることが多いため、身柄拘束中の被告人自身が保釈金を納付するのは困難です。
弁護士であれば、保釈請求に関連する手続きをまとめて代行します。薬物事件に強い専門弁護士は保釈が認められやすい請求方法、保釈金を効率よく集める方法を熟知しているため、確実かつ素早い結果を出してくれます。保釈請求が認められない場合においても、環境を整え、再度保釈請求することも可能です。
治療や再犯防止のアドバイス
弁護士は薬物依存の治療や再犯防止のアドバイスを被疑者(被告人)に行います。被疑者に反省を促すことで、不起訴や執行猶予の獲得を目指します。もし有罪となった場合は、その後の再犯を防ぐサポートを続けます。
指定薬物は非常に依存性が高いです。本人が刑罰を受け、二度と薬物に手を出さないと誓ったとしても、本人だけで更生することは極めて困難です。継続して薬物依存の治療など十分なケアを受けることで、再犯を防止することができる可能性があります。
指定薬物の再犯を防ぐためのポイントとして、本人が本気で薬物を断ち切る意思があり反省していること、薬物の入手ルートが明確で関係者との連絡を一切断っていること、治療に前向きな姿勢を見せていることなどが挙げられます。
弁護士との接見で、薬物依存治療や反省の意思をしっかりと示せれば、弁護士から検察官や裁判官に「再犯の可能性が低い」ことを主張し、不起訴や執行猶予を期待できます。
被疑者に治療や再犯防止のサポートをすることは、本人を更生させることはもちろん、刑を軽くできる可能性もあります。
否認事件の場合
本人が薬物には関わっていない・違法な指定薬物だと知らなかった・知らない間に他人に摂取させられたなどの否認事件の場合には、弁護士は嫌疑不十分による不起訴や無罪判決を目指すべく、証拠を集めます。
警察による捜査段階で「被疑者が指定薬物だと認識していた」という供述を一度取られてしまうと、その後いくら否定しても検察官による起訴は免れず、有罪になり得ます。そのため、否認事件の場合は、供述調書で不利な内容を記載されないための対策が非常に重要です。
弁護士の活動では、被疑者にとって有利になる証拠を探すことがあります。また、被疑者との接見を頻繁に行い、警察からの誘導尋問や自白の強要がないか確認したりします。また捜査時の証拠のねつ造・隠ぺいについても、鑑定された尿や薬物の採取過程などに違法な行為がなかったかを調査します。
捜査時の証拠のねつ造や隠ぺい・自白の強要などは、過去事件でも行われています。被疑者を違法な捜査から守るためにも、弁護士の存在は大きいといえます。そのため、捜査の初期段階から弁護士をつけることがおすすめです。
まとめ
本記事では、指定薬物で逮捕された場合に問われる罪や弁護活動について解説しました。
指定薬物は「合法ドラッグ」などと称して売られていることも多いので、違法だと知らぬまま手を出してしまい、思いも寄らぬところで容疑をかけられることも少なくありません。
指定薬物の所持、使用などの疑いで逮捕された、もしくは薬物依存から脱することができず悩んでいる場合も、薬物事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
この記事を監修したのは

- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
宅地建物取引士